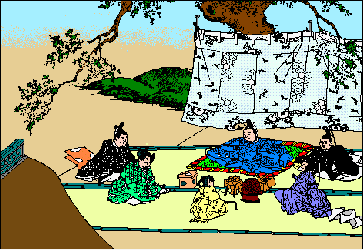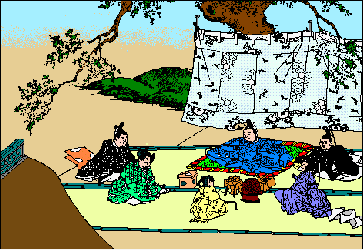-
第 八十二 段 (渚の院)
- むかし、惟喬の親王と申す親王おはしましけり。山崎のあなたに、水無瀬といふ所に宮ありけり。年ごとの桜の花ざかりには、その宮へなむおはしましける。その時右馬頭なりける人を常に率ておはしましけり。時世へて久しくなりにぬれば、その人の名忘れにけり。狩は懇にもせで酒をのみ飲みつゝ、やまと歌にかゝれりけり。いま狩する交野の渚の家、その院の桜いとおもしろし。その木のもとにおりゐて、枝を折りてかざしにさして、かみ、なか、しも、みな歌よみけり。馬頭なりける人のよめる。
世の中に絶えて桜のなかりせば
春の心はのどけからまし
となむよみたる。また、人の歌、
散ればこそいとゞ桜はめでたけれ
うき世になにか久しかるべき
とて、その木の下はたちてかへるに、日暮になりぬ。御供なる人、酒をもたせて、野より出できたり。この酒を飲みてむとて、よき所を求め行くに、天の河といふ所にいたりぬ。親王に馬頭おほみきまゐる。親王ののたまひける、「交野を狩りて、天の河のほとりにいたる題にて、歌よみて杯はさせ」とのたまうければ、かの馬頭よみて奉りける。
狩り暮らしたなばたつめに宿からむ
天の河原に我は来にけり
親王歌をかへすがへす誦じ給うて返しえし給はず。紀有常御供に仕うまつれり。それがかへし、
一年にひとたび来ます君まてば
宿かす人もあらじとぞ思ふ
かへりて宮に入らせ給ひぬ。夜ふくるまで酒飲み物語して、あるじの親王、ゑひて入り給ひなむとす。十一日の月もかくれなむとすれば、かの馬頭のよめる。
あかなくにまだきも月のかくるゝか
山の端にげて入れずもあらなむ
親王にかはり奉りて、紀有常、
おしなべて峯もたひらになりななむ
山の端なくは月もいらじを
この世の中に、全く桜がないとしたならば
春の私の心は、なんとのどかであろうか
散るからこそ、ますます桜は素晴らしいのです
このつらい世に、一体何が変わらずに、いるというのだろうか
日暮れまで狩りをして、織女に今夜の宿を借りよう
天の川という川原に、私は来ていたのでした
織女は一年に、たった一度だけおいでになる、彦星を待つのだから
ほかに宿を貸してくれる人など、絶対にないと思いますよ
まだ心ゆくまで見ていないのに、こんなに早く月が隠れるのか
山の端が逃げて、月を入れないでほしいものです
どこもかも一様に、峰も平らになってほしいものだ
山の端がなかったならば、月も入りはしないから


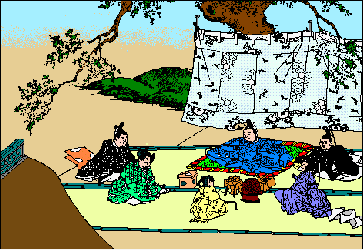
語 句
現代語訳