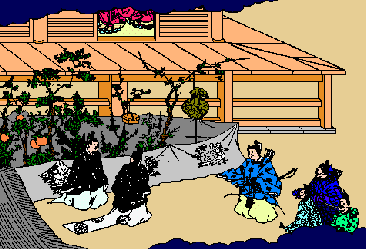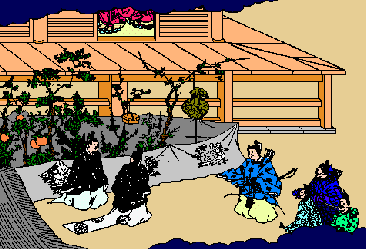-
第 七十八 段 (山科の宮)
- むかし、多賀幾子と申す女御おはしましけり。失せ給ひて、なゝ七日のみわざ安祥寺にてしけり。右大将藤原常行といふ人いまそかりけり。そのみわざにまうで給ひてかへさに、山科の禅師の親王おはします、その山科の宮に、滝落し、水走らせなどして、おもしろく造られたるに、まうで給うて、「年ごろよそにはつかうまつれど、近くはいまだつかう間つらず。こよひはこゝにさぶらはむ」と申し給ふ。親王よろこび給うて、夜のおましの設けさせ給ふ。さるに、かの大将出でてたばかり給ふやう、「宮仕への初めに、たゞなほやはあるべき。三条の大行幸せし時、紀の国の千里の浜にありける、いとおもしろき石奉れりき。大行幸ののち奉れりしかば、ある人の御曹司のまへに溝にすゑたりしを、島好む君なり、この石を奉らむ」とのたまひて、御随身、舎人してとりにつかはす。いくばくもなくて持てきぬ。この石聞きしよりは見るはまされり。「これをたゞに奉らばすゞろなるべし」とて、人々に歌よませ給ふ。右馬頭なりける人のをなむ、青き苔をきざみて蒔絵のかたに、この歌をつけて奉りける。
あかねども岩にぞかふる色見えぬ
心を見せむよしのなければ
となむよめりける。
満足していないけれども、岩に私の気持ちを代えさせます
色には見えない私の心を、お見せする術がございませんので
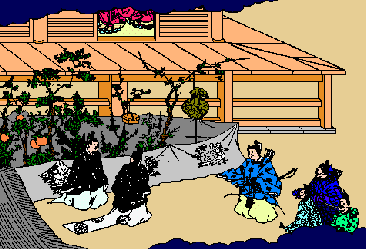
語 句
現代語訳